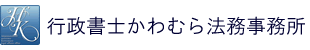名古屋市を始め愛知県を中心に遺言・相続手続、法人設立、薬事法許可申請、名古屋入国管理局への申請等を支援する行政書士事務所です。
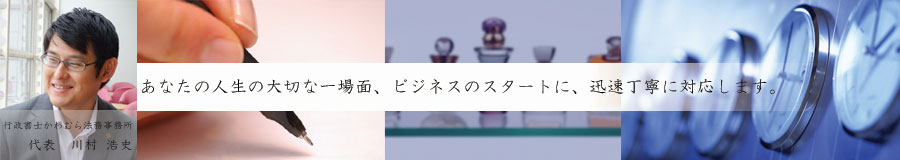
基礎知識2「遺言書には種類があるって本当?」
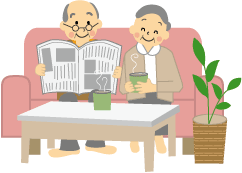 遺言は、亡くなった後に遺言書の効力が生じるものですから、その内容は矛盾や疑問の余地がないように明確に伝わるものでなくてはなりません。
遺言は、亡くなった後に遺言書の効力が生じるものですから、その内容は矛盾や疑問の余地がないように明確に伝わるものでなくてはなりません。
そこで民法では厳格な遺言の方式を定めています。
その方式を守って作成されたものでなくては有効な遺言書とはなりません。ではその方式にはどのようなものがあるのでしょうか?
遺言の方式
民法で定められた遺言の方式には、普通方式と特別方式があり、その方式ごとにまた数種類の遺言の方法があります。特別方式はかなり限定された状況下で認められるものですので、 ここでは一般的な普通方式の遺言の方法3種類を解説します。
1.
自筆証書遺言
 遺言者本人が日付まで含めて全文を自筆で書き押印する形式で作るものです。
遺言者本人が日付まで含めて全文を自筆で書き押印する形式で作るものです。
最も簡単に手軽に作成でき、遺言の内容の秘密が保ちやすいという利点があります。
しかし紛失・未発見・偽造などの恐れがあること、正しい形式かどうかを事前にチェックする機会がないため、 有効な遺言書と認められない恐れがあることなどが欠点です。
2.公正証書遺言
 遺言者本人と立会人2名が公証人役場に行き、遺言者の口述をもとに公証人が作成するものです。最も確実な遺言の方法であり、形式ミスによる遺言の不成立の心配がありません。
遺言者本人と立会人2名が公証人役場に行き、遺言者の口述をもとに公証人が作成するものです。最も確実な遺言の方法であり、形式ミスによる遺言の不成立の心配がありません。
しかし、ある程度の費用も労力もかかるので、遺言の内容を何度か変更する可能性がある場合はお勧めできません。また遺言の内容の秘密保持のためには立会人を誰に頼むかが重要となります。
3.秘密証書遺言
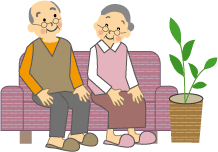 自筆証書遺言と公正証書遺言の間をとった形式になります。
自筆証書遺言と公正証書遺言の間をとった形式になります。
遺言者本人が作成した遺言書を、公証人と立会人2名の前で封印し、公証人の証明を受けることになります。
遺言書の内容の秘密を保持したまま公証人役場に保管されるという利点がありますが、形式の不備がある場合無効になる恐れがあります。実務上はあまり利用されていません。
以上が一般的に利用されている遺言の方式です。
それぞれに利点・欠点があるため、ご自身の状況に合わせた方式を選び、欠点を補う工夫をする必要があります。
自分にはどの方式があっているのかよくわからない、もっと詳しい方法を知りたい、ちょっとここだけ教えて欲しいなどなど、分からない事がありましたらぜひお気軽にご相談下さい。